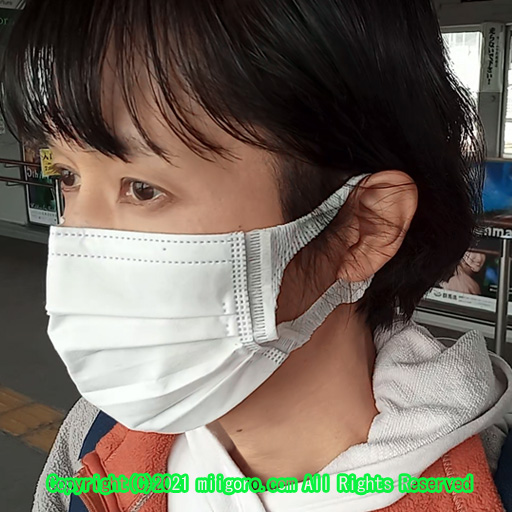絵画制作難航中!
こんにちわ。ミーゴローです。
昨日は午前中いきなりのゲリラ豪雨でした。なんだか、今年は秋の訪れが早いようです。
体調がすぐれません。はしかが流行っているそうですが何かの風邪みたいです。だるくて起きるのが大変です。
ぐずぐずしていると、たちまち路面温度が低い季節になってしまいます。体をはやく直して何とか二輪に乗る時間を作りたいものです。
(バイク関連・モトGP・コラム)
昨日の記事ですが、膝擦りというのは膝を横に出すのでは無くて下に出すと表現した方がいいのでは、ということです。
意外にハッキリこのことを書いている例を見ないのです。ライダースクラブのライテクでも、「イン側の下側にだらーっとした感じで重心を預ける」、とかは書いているのですがサーキットコース上が前提のようです。
ケニー佐川さんの膝擦りの動画で、「膝は下へ前へ」とおっしゃています。それがしっくりきます。
大体、スポーツバイクに跨っ他状態で膝を横に出してみたら分かりますが、膝を横に出した状況で膝を擦る状況というのはカウリングが相当地面に近くなります。
つまり、公道では速度を出せませんので膝を横に出すというよりは、下に出すことを意識した方がいいと思います。そのときリーンアウト(にせリーンアウトといいます)で上体をアウト側に起こしておきます。
「無理擦り」でいいのだと思います。
もしモトGPのように、完全にリーンインで膝を擦っているならコーナーリング速度が速すぎるといえます。
絵画制作難航中
さて、今日の記事は絵画なのですが、絵画以外の方も模型やバイクの塗装にも関連しているので一読してくださると、何かのおり参考になるかもしれません。
秋の展覧会に向けて、現在絵画を3枚制作しているのですが、最初の1枚が完成直前でストップしてしまいました。
原因は絵の具の素材特性についての問題が出てきたためです。
洋画なのですが、ジャンル的には油彩画、つまり油絵ということになります。しかし、実際には現代作家のほとんどはテンペラ技法などの混合技法という手法を用いています。
この手法で描かれた作品というのはいわゆるプロの絵になります。公募展などで日曜画家の人たちが「いったいどうやって描いているのだろう?」と感じる絵になります。
普通の技法、つまり油絵の具だけでそのまま描いてもこういったプロの絵は再現できないのです。こういった作品が地方の自治体の美術展でも入選して受賞しているので日曜画家の人たちには公募展というのは敷居が高くなっているわけです。
混合技法
混合技法というのは、その名のとおり、技法を混合しているのです。つまり、油絵の具だけではなくて、テンペラ絵の具(卵で造った絵の具)やアクリル絵の具を併用する技法です。
この方法を用いると、素人ではできない透明感や独自の絵肌が出てきます。
現在、私が行っている技法は油絵の具とアクリル絵の具の併用です。
基本的にはアクリル絵の具で下地から描いていき、仕上げに油絵の具で仕上げていきます。作風はテンペラ技法で描いた作品に似てきます。
透明なレイヤーを重ねたような絵になります。
油絵の具の上にアクリル絵の具は塗れない
さて、今までの我々作家の常識として、「アクリルで描いた下地の上に油絵の具を塗ることは可能であるが、その反対に油絵の具で描いた上にアクリル絵の具は乗らない。」というものがあります。
理由としてはアクリル絵の具は水性であり、油絵の具は油性であるために親和しないということなのですが、これは少々矛盾しているのです。すなわち、それならアクリルが下地の場合なら油絵の具が乗るというのは説明がつきません。
一般的な解釈としては、「アクリルが硬化したなら水分は抜けて樹脂層となり油絵の具をはじかずに定着させることができるのだ。」というものです。その反対に「油絵の具の塗装面の上にアクリル絵の具を塗る場合は、アクリル絵の具の水分が油絵の具の油分にはじかれて定着しない」といわれていました。
しかしこれには重大な矛盾点が存在します。実は、アクリル絵の具は水性だとはいえ、界面活性剤成分を含むので油となじむのです。もっといえばアクリル絵の具と油絵の具は混ぜることができます。それで使用することもできるのです。
よって、油絵の具の上にアクリル絵の具が定着しないのであれば、アクリル絵の具の上に油絵の具が定着するというのは説明がつかないのです。
実は、アクリル絵の具と油絵の具を混ぜて使用する作家もいます。逆にアクリル下地は油絵の具となじまないとしてアクリル絵の具を下地に使用しない作家もいます。
これらはいまだに結論の出ない課題なのです。つまり、100年後に作品がどうなっているのか現時点では分からないのです。
この点少々疑問に思いまして検索いたしましたところ、Yahoo知恵袋でこれに関する記述がありました。
ベストアンサーによると油絵の具の塗装面の上にアクリル絵の具を塗ると、一見定着したかのようにみえても必ず剥がれてくる。ということです。理由は油絵の具の乾燥しきれない油膜面があるからだそうです。
実は、長年私もそうなると思っていました。それで、今回の作品は剥がれることを表現の効果にしようとして油絵の具の塗装面の上にアクリル絵の具で描きこんでみたのです。
しかし、全然剥がれないのです。つめで引っ掻いてもテープで剥離させようとしてもまったく剥がれない堅牢な塗膜面ができてしまいました。
Yahoo知恵袋のベストアンサーのように剥がれる場合は確かにあります。私も実際にそういった状態を何度も見たことがあります。
この場合、油絵の具の硬化と乾燥が不完全であったと考えられます。さらに原因の本質は油膜ではなくて伸縮性の違いなどによるものではないかと思います。
塗装でいえば、下地の脱脂を十分に行わなかった場合が参考になります。
たとえばプラモデルの塗装でいえば、型抜き剤を落とすために中性洗剤でパーツを洗います。
しかし、これをしたとて型抜き剤は残っており単なる儀式であるという人もいます。実際、やはり型抜き剤は残留しています。それでも塗装はできるのです。
これは、残留している油分や型抜き剤は、塗料に含まれている有機溶剤によって油膜がやぶられて塗料とパーツの基材は良好な密着を実現しているからです。
つまり、もともとある程度の親和性があるなら、少々の油分は問題無いということです。
反面、金属に対する塗装では、脱脂は徹底的に行う必要があります。金属と樹脂である塗料は親和性など無いからです。塗料は金属表面のわずかな凹凸に食いつく状態で安定することになるわけです。
絵画の絵の具の場合
絵画の絵の具の混合技法の場合、問題なのは実は伸縮性だということでは無いかと思います。
ネット検索でもこの点の考察は行われていないようで、なかなか参考となる資料が見つからなかったのですが、ようやくターナー色彩株式会社のサイトで解答といえるものを発見しました。
「油絵具とアクリル絵具の寿命に関する考察」(ターナー色彩株式会社http://www.turner.co.jp/art/golden/technicaldata/justpaint/jp12/longevity.html)によると、油絵の具の上にアクリル絵の具を塗った場合の塗膜の弱さの原因は、硬化した油絵の具の表面が滑らかすぎるためだということでした。
なんと油膜では無かったのです。油絵の具の乾燥・硬化のメカニズムは油の揮発ではなくて、絵の具に含まれる乾性油が酸化する化学反応である、ということです。よくあるように、油絵の具の乾燥を速めようとドアリヤーで暖めたりはほとんど意味が無いということです。
アクリル絵の具による下地に油絵の具が安定して密着するのは、アクリル絵の具の硬化後の表面は非常に凹凸が多いためだということです。
これらの事実は、アクリル絵の具を油絵の具の上に塗っても問題無いということではありません。やはり、不安定な塗膜であるということには変わりはありません。
しかし、実は油絵の具だけで描いたとしても、伸縮性の違いからの劣化は想像以上に大きくそれらとあまり変わらないのかもしれません。むしろ、油絵の具の天然樹脂とアクリル樹脂との伸縮性の違いに注意するべきだと思います。
きょうもこのブログをお読みくださり、ありがとうございました。