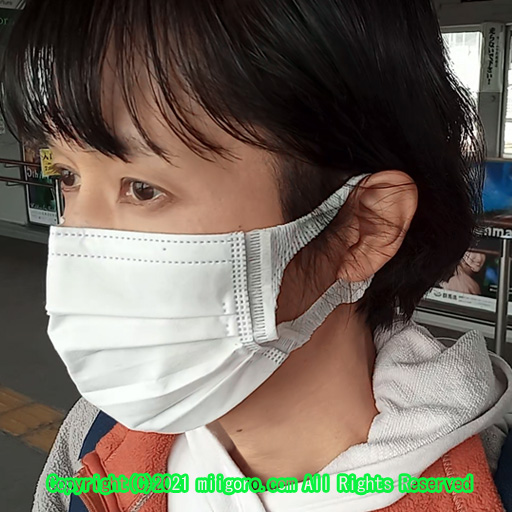クマ対策に自衛隊派遣要請について
瞳です。本日二つ目の記事。
最初に少し。自衛隊員の待遇改善法案が、高市総理によって今国会に出されることになりました。これは、実に素晴らしい快挙です。
小泉防衛相の財務省圧力慎重論を一喝したうえでのことだったとのことです。
やはり、高市総理は、世襲馬鹿をちゃんとコントロール下においています。
さて表題なんですけど、鈴木健太・秋田県知事の要請を受け、11月5日、県内でクマ対策のための自衛隊派遣が始まったそうですが、わたしの過去記事にもありますように、自衛隊の装備では、自衛隊員が危険であるということを書きました。
過去記事では、89式自動小銃の5.56mmNATO弾では威力不足であり、7.62mmNATO弾を使用できる銃器が必要であると書きました。さらには、30-06エンフィールド弾の方がいいと思いますと書きました。
89式自動小銃の5.56mmNATO弾では威力不足の意見は、他の方、元自衛官の方も言っておられましたが、
で、気になる動画がありまして、髭の隊長こと佐藤正久さんがですね、自衛隊の銃は、銃弾がフルメタルジャケット(銃弾の鉛を銅でカバーしているタイプ)なので、クマの体を貫通して跳弾が一般市民に危険であるから発砲行為はできない。との趣旨の発言がありました。
この方はイラク派遣で現地指揮を担当していた実績もあり、その発言は当然専門なので信頼するべきものなのです。それについて、追記します。
そもそもですね、5.56mmNATO弾がクマの体を貫通するとは思えません。さらに、この銃弾はタンブリング現象という特性があり、対象物に命中すると、その対象物の体内でプロペラのようにクルクル回りまして、傷口、及び内部の損傷を複雑化させる特性があるわけですね。
5.56mmNATO弾には4種類ありまして、タンブリングしないタイプも2種類ほどあるのですが、自衛隊の使用する銃弾はタンブリングするタイプだというのを、どこかで聞いたような記憶があります。
よって、髭の隊長こと佐藤正久氏の言ってるのは、おそらく7.62mmNATO弾の使用を言っているのだと思います。
でもまあ、せっかく自衛隊が出て来るのに、後方支援だということで、自衛隊が出動すべきかどうかという意見が大勢です。
しかし、過去に自衛隊がクマ被害対策で出動した例は、ヤフーニュースの11/7(金) 11:12配信の文春オンライン『クマに対して自衛隊が出動したのは過去に8ケース』によれば、「熊害で自衛隊が派遣された例について、筆者の調べでは1960年代に北海道から東北にかけて8件ある。最も古いものは、1961年9月の海上自衛隊函館基地隊によるもので、北海道松前地方でクマによる農作物の被害を受けた地元の要請で、自衛隊員3名と猟銃5丁が5日間出動したと『自衛隊年鑑』にある。 猟銃が出ていたことから、駆除に関わった可能性もあるかもしれないが、活動の詳細やどのような根拠法による派遣かは定かではない(災害対策基本法の施行は1962年7月10日である)。
最も大規模なものと思われるものは、1962年10月の北海道標津町の古多糠集落への派遣だ。この派遣については、 過去にも文春オンラインで記事 を公開しているので詳細はそちらを参照して頂きたいが、クマの出没や家畜・人身被害が相次いだため、M16対空自走砲2両を含む部隊が災害派遣され、学童の輸送やパトロール活動を行っていた。 しかし、住民から駆除への参加を強く求められたため、派遣部隊が銃による駆除活動に参加したことが『週刊読売』で伝えられている。」
ということで、少し映像も見ましたが、自衛隊員は全員ちゃんと大口径ライフル(種類は見えない)を携帯しており、記事にあるように多連装対空機銃まで投入していてびっくりしました。これ、おそらく口径12.7mm50口径のM2機関銃のタイプなんでしょうけど、いわゆるこの50口径ならクマにも十分すぎるほどの威力があります。
前例あるんならこれが一番手っ取り早いのに。
クマを完全に粉砕できます。大戦中の米軍戦闘機が搭載していたもので、大戦末期には機銃掃射をしまくりまして、線路のレールも厚みのある上方から完全に貫通していて驚きました。
しかしまあ、なんで自衛隊が撃てないんでしょうね。鈴木健太・秋田県知事は元自衛官なのだそうで、当然自衛隊の攻撃能力での協力を依頼したのだと思います。
跳弾の問題ですけど
もしね、街中にクマが出てきたら、警察の狙撃班もライフルは使用できません。
でね。そんなときですね、自衛隊の装甲車で、麻酔弾撃つというのはどうですか。
即効性が無いので、危険ではありますけど、装甲車複数台で挟み撃ちで囲うとかしたらどうですか。
麻酔弾なら、お花畑の動物愛護のおばさんたちも文句言わないでしょう。後で殺処分ですけど。
ついでなんですけど、クマ擁護の連中、クマと一緒に檻に入れたら自分の馬鹿さ加減が理解できると思います。おばさんたちを二重の檻に入れて一応保護してですけど。クマのハリテ一発で卒倒です。パンダと完全に混同してますからね、連中。