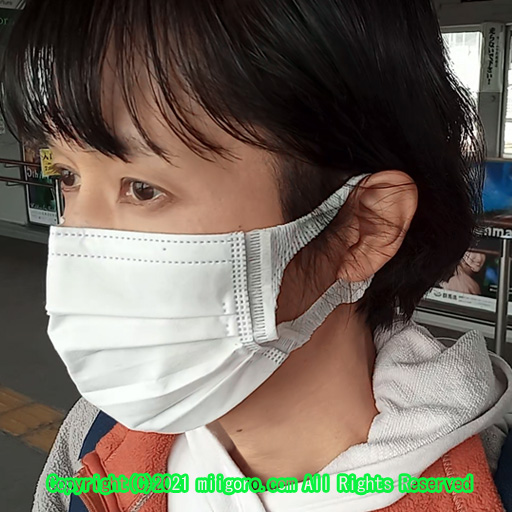女王の教室
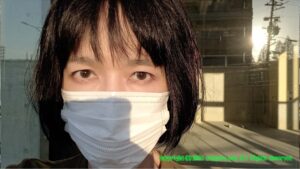
こんばんわ。制作は一段落しました。しかし、油断せずに、すぐにやってくる秋の本展に向けてもう一枚100号の制作始めておくべきなんです。制作の感覚がアクティブなうちにも。
何せ、まもなく猛烈に暑くなりますから。
いつも、寒さ、暑さで苦しみます。分かっているんだけれど、なかなかできません。我ながらいつまでも学習できてません。
奈良市内にあった、実家のあの広くて、空調のあったアトリエが本当に恋しい。義理の妹のせいでもう無いんですよ。
ネコのみぃちゃんも、もうついてくれていないし。
奈良市内のあの夜の静けさというか、独特の世界、本当によかった。あの独自の雰囲気がもつ気配。春日大明神のおひざ元の聖域がもつ世界。大学生時代の頃の、大学に泊まり込みで制作していた頃も、おなじ世界の中にいた。今思い起こせば、まったく夢のよう。
この3日間は、ふらふらで何もできませんでした。昨日も一日中眠ったまま。そういえば、今日が市立美術館への搬入だから、今日からさっそく審査が始まるわけだけれど。別にあんまり気にならない。
女王の教室
で、表題なんですけど、このドラマのショート動画、今、休みながら惹きつけられるように見続けてます。
懐かしいというより、何か怖い思いでが蘇ってきます。自分の教師生活の。
2005年のドラマだそうですけど、天海祐希さんが言ってること。全く真実じゃん。まるで、今現在、重大問題になっている社会世情そのまま。
「少数の数パーセントの富める者たちのために、一般人が奴隷のように働き搾取されている。」とか、「そういう特権階級は、民衆がいつまでも、愚かで、無知で、従順なままでいて欲しいのよ。」とか、よくまああの時代に放送できたもんだわ。まあ、あの時代だからかな。
よくまあ、放送できたもんだわ。
わたしの教師生活というか、わたしもけっこう無茶苦茶でしたが、あれほどではない。
あのね、どうせドラマだから、とか思われるでしょうが、かなり子供たちとか親とかリアルですよ。教師の方々なら分かるはず。あんな感じです。実際。
わたしも小学校が一番しんどかった。勤務も小学校が一番長い。思い出しても、あの日に帰りたいとか思わない。とにかく、しんどかった。
これ、誤解の無いようにいいますけど、子供たちや親が酷かったという意味ではなくて、学校という組織システム、存在があまりにも馬鹿なのでそれで、疲れ果てました。
その因習的なシステムのせいで、教師はいうまでもなく、子供たち、親たちもクタクタなんですよ。全員被害者。
今は昭和ではない
まあ、簡単に言えば、分かりやすく言えば、平成、令和でも昭和のシステムのまま、価値観のままなんです。とにかく上意下達。文科省、中教審がどうのというより、教育システム、組織が劣化崩壊している。
これからはICTだといって、こども一人に端末1台はいいとしても、その端末が使い物にならない。これはまだ、無理がある。やたら重いし、重量も、動作も。
老害だね。老人には口出しさせないこと。
ICTとかコンピューターのこと、全然分かりもしないのに「これからはICTだ。」とかいい加減なこと口出しするから、とか中途半端なろくでもない結果でむしろ現場が振り回される。
だから、九九もできない子が出てくる。
いくらAIの時代とはいえ、まだまだハード、ソフトともに性能は不足している。
「読むこと、書くこと、暗記すること」を軽視してはいけないし、学校、教師は授業を最優先するべきであって、行事は付随するものに過ぎないということ。を再認識するべきです。
部活の幻想
なんども書きますけど、部活を民間に完全に委託するのは極めて有効です。ただし、費用は教育予算で賄うべき。「子ども家庭庁」なんてやるお金あるんなら、できるはず。だから経済格差は関係しないし、生じさせない。
そして、学校単位のチームではなくてもいい。むしろ、学校単位のチームであってはならない。よけいな「大会優勝をねらう。」とか、教育とかけ離れた勝利至上主義を排除するためにも。
また、学童保育のように、施設は学校のグランドを使用してもいい。でも、学校から、部活を完全に切り離す必要があります。
つまり、とにかく部活は、学校組織とは全くの別組織にすること。先生たちは一切部活には関わらないこと。これ、絶対条件。
こういう形態は、学童保育ですでに実現しています。これ重要なことで、すこしでも、教員に「顧問」という肩書を残そうものなら、結局、その顧問は何かにつけ同じように休日出勤やら放課後に顔を出す必要が出てきます。(たとえ、ただ見ているだけで、何もしなくても。)それが、学校という組織。
「ねずみさん」の動画でおっしゃっていたんですけど、部活がなくなったら、行き場を失った連中が公園やらで悪さをするとか、いろいろ懸念を挙げられるているんですけど、だからね、スイミングスクールみたいに、完全に業務や責任を民間に移譲して独立させるのよ。教育予算で。場所は校庭、グランドでいい。ただし、先生たちは一切関わらない。見物もしない方がいい。(事故が起こった時、責任を問われる危険があります。)
この、部活の弊害というのは、一般の方々は想像もできないでしょうが、地域の干渉(これ大問題で、実際の事例も多いです。勝たせたい親とかOB、地域の有力者の存在は悪弊の極みなんです。別記事で書きます。過去記事でも少し書きました。)も大問題で、子供の学力を確実に低下させます。つまり、教師の教育能力を低下させます。
部活に熱心な子たちが、すべて推薦で進学できるわけでもないし、部活推薦で入れるような高校、大学はその程度だという事実。
いま、習い事のトップは水泳教室なんだそうで、何考えてんだろう。親御さん。水泳が一体、将来に何の役に立つの?
まあ、私自身、剣道(かなりキツイ道場、手加減無しの打撃、防具の模様のあざがつくくらい。息は上がるし、痛いし倒れるまででしごかれた。)や空手(極真フルコンタクト空手)の荒稽古経験していて、それだからその「無意味」さを知ることが出来て、また知っているわけだけれど。また、だから、中学での半殺しのリンチ暴行いじめにも身体は何とか骨折もせず耐えられたわけだけれど。(反撃しなかったの。自己防衛しなかったの、と思われるでしょうが。相手が一人のときならぶちのめしました。でも、男子の不良グループの番長がこれまたデカくて、こいつにだけは勝てないと直感。結局、複数で殴る蹴るされて、毎日あざだらけ、血だらけ。親は見て見ぬふり。本当の親じゃないし。)
まあ習い事なんですけど、この「無意味」の苦労を一度は経験しておくこと自体は無意味ではないです。確かに。
しかし、没頭しすぎて、家の経済を圧迫したり、勉強に差しさわりが出て来るなら本末転倒。やり過ぎです。そろばんや、習字、公文式をやる方がよっぽどいい。
そして、繰り返します。
「勉強がすべてではない」などというのは、嘘です。
学校は子供の学力確保を最優先、第一目標にしなくてはなりません。つまり、授業を最優先にするべきで、行事や慣習は淘汰しなくてはなりません。
で、「いい加減、目覚めなさい。」
これ、わたし、実際に言ったことがあります。関西訛りで。
子供の反応は、「受け狙いめ。」だったけど、管理職、同僚にはかなりやりました。セリフを言ったのではなくて、授業方針やらのいろいろ反発。今思えば、無茶苦茶でした。我ながら。
まあ、○○市でわたしは名物で、私の名前は知れ渡っていました。