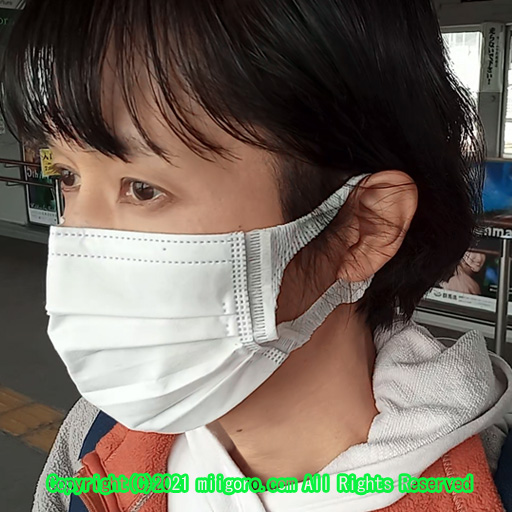小説「ユートピア」2
分断家族
この、まるで見知らぬ老女。姉、浩子の変わり果てた姿に言葉を失う。
原因は明白だった。認知症であろう母、高齢の恵子の介護がもたらした結果だ。
おそらく、想像を絶する苦労の結果なのだろう。
この姉、浩子が数年前、行方不明になる前、最後に言った言葉を思い出す。
岬の問いに答えた言葉だ。
「お母さんの介護、どうするんですか。」
「母親の介護はわたしがみる。だから、あんたとはこれっきり永遠にさよならよ。」
当時、(介護ってのを分かっているのかね。この人は。)岬はそのとき思った。
「自宅介護は地獄」だ。という現実、真実。
実際、介護の生活苦から、自ら〇を絶つという悲劇、事件もよく耳にする。
まあ、この母親の年金、遺族年金、を含めたけっこうな額の年金目当てだったのは明白なのだが、あまりにも、この姉の考えの浅はかさには呆れたのを思い出す。
しばしの会話の中断の後。改めて話を進める。
とにかく、玄関にも入れてもらえないのだが、さすがに母、恵子のことも気がかりだ。
それでも、「あんたに今合わせたら、混乱するだけや。帰って。」と、相変わらず取り付く島もない。
まあ、母、恵子は、おそらくわたしのことすら、会ったとしても分からない状態なのだろう。と察する。
それでもしかし、もひとつ気がかりというか、確認しておかなくてはならないことがある。
聞くのも気が重いが、
今の岬がひとりで住んでいる物件に関して、抵当はかかっているのか。ということを確認しなくてはならない。つまり、母親名義の不動産を担保に、どこからか、借入はしているのかということ。
そして、もし、担保権がかかっているのなら、その担保は消滅するのだということを、この姉に知らせておかなくてはならない。
のだが、予想通りの反応。
「あの・・・ちょっとお聞きしますが、あの物件に抵当権はかかっていますか。」
言うが速いか「あんた、それが聞きたかったんやろ。結局それが目当てか。」
で、ドアをガチャンと閉める。
(違うのよ。抵当権がかかっていたら、あとであなたが困るから、保証人を親戚に頼むとか、わたしが引き受けるかしないと大変になるから、って伝えにきたのよ。)
しかたがないので、ドアを軽くノックする。とにかく、団地は音が響くから何かと気を遣う。
再びドアが開いて、「抵当権かかってるんですか。」と再び確認する。
「だから、そんなこと、あんたに教える義理は無い。帰って。」
再びドアをガチャンと閉める。(この人、近所迷惑とか考えないのかね。もしかして、近所と孤立してるのかな。)とか、思うのだが。まあ、それっきり再びドアが開くことは無かった。
まあ、こうなるとは思っていた。やっぱりね。
バイクに戻って、エンジンをかける。もしかしたら、母親の恵子が窓から見てるかな、とか思ったけど、窓には人影は無かった。
来る時とは別の道を帰る。やや遠回り。春日大社の前を通って、母校の大学の前を通り、護国神社の横を通って帰る。
心を落ち着かせたかった。
やっぱりね。わたし、かなり、堪えてるのかな、と自分でも思う。(あの態度はやっぱり酷かったね。)
放浪家族
岬は帰り道で、ふと今更ながらに思う。そもそも、この今の状況。この家族の状況というのも、思えば不自然に過ぎる。
養女の岬が、持ち家の世帯主で、その本来の不動産の持ち主である両親と家族がその家を出て借家に住むという状況。
しかも、その住処は転々として定まらない。最後は奈良市の一等地であった。・・・のだが、その後がさっきの団地ということになる。
そういえば、この状況というのはいつからだったのか。きっかけは何だったのか。
そうだ、とある啓発セミナーが始まりだった。
セミナーというか、私設のカウンセリングルームだ。もちろん非合法。
フランス人の私立大学の教授が、副業として開業していた。
この教授は、専門が社会心理学。その肩書で当時たしか数人、うちの家族を合せて10人程度に対してカウンセリング療法を行っていた。
報酬は一回30分だったか1時間だったか、で1万円。
ここに、当時存命だった父親も含めて3人が家族カウンセリングなるものを受けていた。それに加えて、姉の浩子、母の恵子がそれぞれ週に2回個人カウンセリングを受けていた。
けっこうな出費である。
岬も、それに無理やり何度か付き合わされたことがある。
まず、行ってみて場所からして驚いた。
大阪、大正区の在日外国人の多い団地の一室。
民度は低い。大阪環状線、大正駅から歩いて行けるのだが、途中みかける付近の住民は子どもからしてよろしくない。よくもまあ、こんな場所で。と思ったのを記憶している。
おそらく、この教授は、もとはこの付近に住んでいたのだろう。よくもまあ、ここからDランクの私立大学とはいえ、大学教授までのし上がったもんだ。それは大したものだと感心する。
多分、祖国での研究実績がそれなりにあったということなのだろう。
洗脳
岬は、最初からこの教授のカウンセリングには批判的であった。
カウンセリングの基本的スタンスは、「非指示的カウンセリング」を守ることである。
すなわち、カウンセラーはクライアント(相談者)に対して、具体的な指示を出してはいけない。
具体的な指示を出すことは、きわめて危険なのである。
しかし、この教授は違った。セオリーを無視していた。
ここのカウンセリングルームに来るクライアント(相談者)に対して、かなり具体的な指示、アドバイスをしていた。
カウンセリングの絶対的基本は、「非指示的カウンセリング」を維持することである。すなわち、カウンセラーは、傾聴、共感、受容の態度で接し、クライアントが自分自身で何かを気づき、問題を解決できるように導くことである。
指示的対応をカウンセリングに取り込むことは、洗脳につながる危険をはらむ。
岬はこの指示的対応に対してまず批判した。しかも、報酬を取ることにも言及した。それに対する答えは、
「Give and Take.」の哲学です。と流ちょうな日本語で答えてくれる。
どこがこれ、哲学なの。と思う。そうか、この人にとってはビジネスも哲学と割り切っているんだ。
まあ、しょせん外人さんだわね。こんなもんだわ。
岬は自分をもっていた。言い換えれば、自分で物事を判断し、決断することしかできなかった。
だから、結局、この教授とは考えが合わなかった。といえる。
依存
ここのクライアントは、いわゆるニート、当時でいう「ひきこもり」の人が主であったと思う。
これらの人たちを、教授は一応社会人にすることに成功しているようだった。
これは、大したものなのだが、重大な懸念を岬は感じた。
ある日のこと。あるカウンセリングセッションに付き合わされた時、制限時間を過ぎてしまった。馬鹿な姉の浩子が熱中しすぎたのである。カウンセリングと名付けられたただの会話に。
そして、部屋のブザーが鳴った。つぎのクライアントがやってきたのである。
しかし、なかなか終わることができない。またまたブザーが鳴る。何度も鳴る。
ようやく、話を終わらせ、部屋を出るとき、その次のクライアントと顔を合せることになった。
その人は、スーツを着たサラリーマン風。つまり、一応社会参加に成功しているのだろう。
しかし、なぜ、まだここに来る。そして、なぜ、あれほど執拗にブザーを鳴らさなければならないのか。少し待つ、ということができなかったのか。
さらに、岬たちを見ても悪びれない。ブザーをしつこく鳴らしたことに対して何も感じていないのか。
なによりまず一番気になること、(あなた。まだ、どうしてここに来るの?)と岬は思う。
この人は、まだ自立できていない。これは、本当の自立ではない。この人は、依然としてまだ、ここを必要としている。これからもずうっと。多分。この人は結局また潰れるのではないか。
岬のこの予感は的中することになる。
この教授は、あまりにも善人だった。本当の姿は「Give and Take.」を哲学と定義する合理主義者ではなかった。
いつしか、報酬も取らなくなった。まるで、完全な孤軍奮闘のボランティア活動である。
そして、曖昧な記憶だが、6人ほどのニートの人生の重み、苦しみ全てを完全に背負い込んでしまっていた。
結果。その重みで自〇してしまった。妻と子供を残して。
負の遺産
善人であった教授ではあるが、岬の家族には負の遺産を残すことになった。
まず、岬を残して家族3人で家を出ることを提案したのが彼だったのだ。
岬は教授の信者にはならなかった。
教授の理想の家族像に、岬は邪魔だった。
また、姉の浩子との軋轢が家族不和の原因であること、両親共に無学で、家族で岬だけが国立大学であり、浩子はFランク短大卒であることも問題であるということらしい。
実は、この分析自体は正しい。何から何まで岬と残りの3人とは合わないのである。家族内では衝突が多かった。
岬の家庭内の権力は、養女であるにもかかわらず強かった。知識と教養、学歴は家庭内でも強い力を持つのだ。
学費は国立だから安い、と言う以前に全額免除が認定されていたから恩もへったくりも感じていない。
母の恵子がよく「だれのおかげで大学行けたんや。お金無かったら行かれへんねんで。」と言うのだが、岬は「わたしは、自分のおかげで大学入れたんや。」と言い返した。
反対に父親は、学歴の無い平凡な人生だった。高学歴ぞろいの名門の本家での法事、集まりなどでは、何かと肩身が狭かったようだ。その反動なのか、その親戚に逢う機会には、岬のことを誇らしげに話す有様であった。
こういった場合、姉の不満、鬱積は相当なものであったのだろう。
こういった家族の無理な歪をかかえた同居は状況を悪化させるばかりである。歪の中心である岬との一時的な別居は、確かにひとつの解決策ではあったのだが・・・
つづく