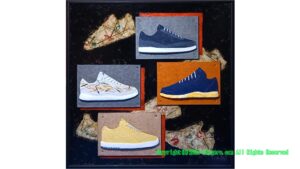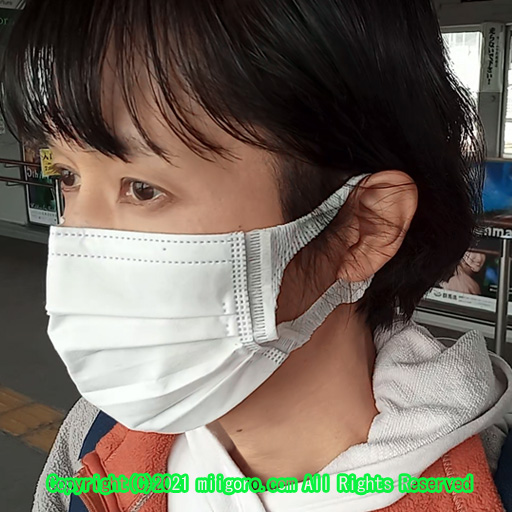公募展に絶対に入選する方法の4・真似をしてみる。
こんばんわ。成海瞳の鬱(うつ)日記です。
ようやく、政治や、社会問題等への記事へのアクセスもくるようになったのですが、あいかわらず、この「公募展に絶対に入選する方法の2」へのアクセスがコンスタントに多いので、やっぱり芸術系の読者の方への記事も、ちょうどシーズンですから書きます。ざらっと。
この公募展の意味なんですけど、『全関西美術展』は、大阪市立美術館のリニューアルも終わったのですが、再開はないようです。
で、わたしの「公募展に絶対に入選する方法の2」へ来られる方々は、おそらく著名美術団体への出品を目指しておられるのかな、と推測いたします。
まあ、結論申し上げますと、何度も今までの記事でも書いてますけど、強豪団体以外は、まあ出せば通ります。(少子化の影響です。)
でも、アクセス数からみて、今でも、もしかしたら落選なさる方もおられるのかな、とか思いますので、ごくオーソドックスな必勝法、書きます。
『誰か、ご自分が惹かれる作家の作品を、まるっきりパクってみる。(技術的なことや、その他いろいろ。)』
これ、在野系(現代アート)の団体では、ごく一般的な上達の手段のひとつで、真似された作家や先生は、別段不愉快な想いはなさいません。みなさん、そうやって、マチェールとか画法、技法のイロハを学んでいくわけです。(職人の世界でいう、「師匠の技を盗む。」という意味。)
まあ、各先生方の作品というのは、その先生秘伝の技法があるわけで、これなかなかうまくいきませんが、トライしてみて下さい。
ちなみに、我が兄貴は、学生時代『二紀会』の生駒 泰充先生の絵に惹かれて、散々悪戦苦闘して真似しようとしていました。しかし、これがなかなか、あの独自の画風。技法からしてまったくの謎。
でも、アクリルで、なんとか感じが出たかな、という作品を「関西二紀会」に出したところ、懇親会で当の生駒 泰充先生から、左手の握手をして頂いたそうです。これ、意味は、「お前は私のライバルだ。」という意味で、お褒め頂いたわけで、大変光栄なことでした。
その後、その生駒 泰充先生の直弟子の方が、大学院に来られて、いろいろ間接的にご指導いただいたりしました。(その方、大変ナイーブというか、変わった人で、兄貴には直接声をかけてこられなくて、他の学生に教えるていで、それとなく兄貴の技法の欠点やらの指摘、技法の秘密とかを教えてくださったりして。ありがたいことでした。)
また、他学から非常勤で来られていた先生が、ずばり、「生駒 泰充先生の作品の独自な画風は、ウィーン幻想派とよばれるテンペラ画法だ。」と教えてくださり、アクリルで再現する方法も教えて頂いたそうです。長年のあの生駒 泰充先生の作品の透明感の謎が解けたといっておりました。
これらの先達、先生方のおかげで、兄貴の晩年の作品は、ほぼおおよそ、技法をマスターしたようでした。
とまあ、つまり真似するというのは、けっこう勉強になりますよ。先生同士でも技術盗み合ってるし。これ本当です。別段、それで険悪になったりはしません。むしろ、技術真似することで賞賛しているわけですから。
それと、もひとつ。
これは、わたしの信条。(絵に思想を入れるな。わざとらしいストーリーも必要ない。むしろ、そんなの無いほうがいい。ふと浮かんだイメージとか、そのまま描くとよい。)
たとえば、自分は学校の先生をしていて、学級崩壊を描いていて、この構図は子供の不安感を表していて、さらに、自分は教師だから、教材教具の詳しいディテールまでちゃんと描いているんだぞ。とかいうお方がおられるのですが、実につまらない絵です。だって、そのままじゃん。何も心に響いてこないのよ。(あっそ。成程ね。大変でしたね。)それだけです。