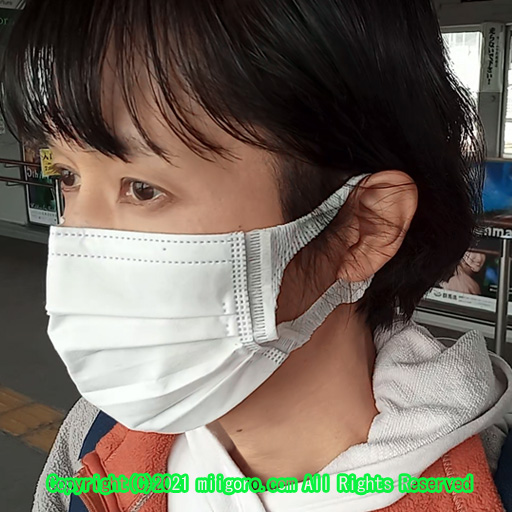クローン猫
こんにちわ。ミーゴローです。
昨日のモトGP決勝ですが、結果的にはほぼ実力順ではありました。内容は大荒れでした。タイヤの耐久性の問題から、決勝レースは20周となりタイヤとマシンの途中交換義務が取り入れられました。中間点の9周目から11週目までの間にマシンを乗り換えなければならないということです。
興味深いのは、ホンダのマルケスなのですが、前半ヤマハのロッシに追い詰められて大変だったのですが、両者マシン交換後はマルケスのマシンの方が仕上がっている感じで差がどんどん
広がってしまいました。
マルケスは予選まで散々転倒していてマシン2台ともにダメージがあるはずなのです。よくもまあ修理したものです。フレームの狂いなどはどうやって修理するのでしょうか。ワークスチームでもメインフレーム交換までは難しいと思うのですが。
まして、0,1mm以下の違いをレーサーは感じ取るといいますからホンダのチーム力というのは凄いと思いました。
マルケスのコメントによれば、「2台目のマシンがフィーリングがよかった。」、とのことですからやはりマシンの個体差は出てしまっていたのでしょうが、よくやるものです。
一方、ロッシは転倒していませんから、2台両方共、完全にセッティングされているはずなのですが、乗り換えてからはっきりラップタイムが遅くなりました。本人のコメントによれば理由は分からないそうなのですが、多分本人の言うとおりタイヤの具合なのでしょう。
それにしても、ひどい路面コンディションでした。こういう路面ではモトGPでもバイクがバンクしないのです。各ライダー大きく膝を出していていました。
これは学ぶべき事です。モトGPマシンがあり得ないバンク角を実現しているのは、タイヤがグリップしている事をライダーが実感できているからなのでしょう。
公道では、タイヤのフィードバックに敏感に従うべきだという事です。
マルケスマシンのホイールの色が濃い
レース後のインタビューシーンでマルケスのマシンを観ていると、ホイールの色が濃いことに気づきました。
以前、タミヤ模型の塗装済み完成品RC211Vペドロサ仕様のホイール色がおかしいと書きました。蛍光オレンジで塗装してあったのです。これは無いだろうと、ホイールのみ作り直して塗装し直しました。
レプソルのオレンジは、タミヤ模型のニューモデルRC213V発売に合わせてニューカラーが発売されましたからやはり蛍光オレンジは無理があったということです。
そもそも、コーポレートカラーというのはメーカーがきっちり指定しますから、マシンカラーがスポンサーの指定色と異なるなど本来はあり得ないことなのです。
でも、模型作りの記事でも書きましたが、ホイールの色が濃く見える写真はありました。色相はおおよそ合っているようなのですが、色が濃いのです。これは光の加減ではなくてホイールの製造メーカーの問題のようです。
昨日の中継では、マルケスのマシンのホイールが前後共、明らかに色が濃かったのです。ペドロサのマシンは普通に見えましたから光の加減ではありません。
面白い発見でした。
クローン猫
猫をよみがえらせるということは、可能なのでしょうか。
映画「ペットセメタリー」では、ろくなことになりませんでした。
別に映画のようなダークパワーに頼らなくても、現在はクローン猫は可能です。費用も推定300万円以下になると思われます。
推定と書いたのは、当初この企画を立ち上げた企業が撤退しているので分からないのです。
大学につてがあるなら、それほど難しいことでもないようです。
生きている細胞を液体窒素で保管することくらいは、大した設備も必要ありませんから大学の研究室にいる方や個人的なつてがある方なら可能でしょう。
クローン猫なのですが、完全なゲノムDNAが必要になります。よくきくDNA鑑定とは、DNAの塩基配列全体の完全な照合をしているわけではなくて、部分照合の確率論によるものなのです。だから、クローンをつくるには毛などの部分ではだめで完全なDNAを含む体細胞が必要になります。
だから、ペットの遺品製造サービスにDNAを封入したものがありますが、ゲノムDNAではなくてDNAの一部分ということになります。
この「遺伝情報の全体」をもつゲノムDNAを含む体細胞か細胞核を卵細胞に移植するということになるのです。
さて、これがうまくいったとして、誕生した仔猫たちは生前の猫と同じ猫だと言えるのでしょうか。仔猫たちと書いたのは複数で誕生することになるからです。
この話、とても長くなりますので続きます。
今日もこのブログをお読みくださり、ありがとうございました。